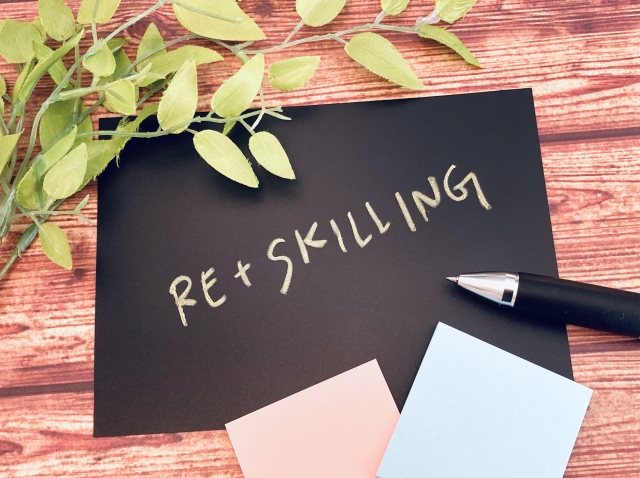技術士試験対策– category –
-

技術士資格の価値と活用法
技術士資格は、技術の高度な応用能力と豊富な実務経験および高い技術者倫理を備えた技術者であることを証明する日本の国家資格です。 しかし、医師や弁護士のような業務独占資格ではなく、資格を持つだけで仕事が発生するわけではありません。 それでは、... -

第一次試験問題〔専門科目〕を解く
はじめに 金属部門の令和4年度技術士第一次試験問題〔専門科目〕を解きます。 全35問中の2問目です。 問題(Ⅲ-2)と解答 問題 高炉(溶鉱炉)製銑プロセスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 選択肢 高炉は竪型炉の一種で、主原料である... -

第一次試験問題〔専門科目〕を解く
はじめに 金属部門の令和4年度技術第一次試験問題〔専門科目〕を解きます。 全35問中の1問目です。 問題(Ⅲ-1)と解答 問題 次に示す一定圧力下における共晶系のA-B二元系合金状態図に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか(図省略)。 選択肢 組成... -

第二次試験問題〔金属加工/鋳造〕を解く
はじめに 選択科目「金属加工」の内容は、「鋳造、鍛造、塑性加工、溶接接合、熱処理、表面硬化、粉末焼結、微細加工その他の金属加工に関する事項」と規定されています。 今回、選択科目の専門知識の一分野である鋳造の学習として、平成19年度Ⅰ-1-1の問題... -

第二次試験問題〔金属加工/溶接接合〕を解く
はじめに 選択科目「金属加工」の内容は、「鋳造、鍛造、塑性加工、溶接接合、熱処理、表面硬化、粉末焼結、微細加工その他の金属加工に関する事項」と規定されています。 今回、選択科目の専門知識の一分野である溶接接合の学習として、平成20年度Ⅰ-1-4の... -

第二次試験問題〔金属加工/熱処理〕を解く
はじめに 選択科目「金属加工」の内容は、「鋳造、鍛造、塑性加工、溶接接合、熱処理、表面硬化、粉末焼結、微細加工その他の金属加工に関する事項」と規定されています。 今回、選択科目の専門知識の一分野である熱処理の学習として、平成20年度Ⅰ-1-5の問... -

第二次試験問題〔金属加工/塑性加工〕を解く
はじめに 選択科目「金属加工」の内容は、「鋳造、鍛造、塑性加工、溶接接合、熱処理、表面硬化、粉末焼結、微細加工その他の金属加工に関する事項」と規定されています。 今回、選択科目の専門知識の一分野である塑性加工の学習として、平成20年度Ⅰ-2-3の... -

第二次試験の出題意図と問題構成
はじめに 技術士第二次試験の金属部門の必須科目及び選択科目について、出題意図と問題構成をおさらいします。 必須科目 まず、必須科目の出題意図、問題構成及び問題内容です。 出題意図 出題意図:必須科目 技術士第二次試験実施大綱に、必須科目の出題... -

【回答】技術士第一次試験_専門科目_金属部門_令和元年度_Ⅲ-10
分類:金属材料(強化機構) 問題:金属材料の強化機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。① 面心立方構造の金属では、結晶粒径に加えて積層欠陥エネルギーも加工硬化挙動に影響を及ぼし、一般的に積層欠陥エネルギーが小さいほど加工硬... -

【回答】技術士第一次試験_専門科目_金属部門_令和元年度_Ⅲ-9
分類:金属材料(フィックの第二法則) 問題:静止系における一次元の非定常拡散現象を記述するフィックの第二法則を表す式として、最も適切なものはどれか。ただし、Cは濃度、tは時間、xは距離である。Dは拡散係数で、濃度によらず一定とする。① δC/δx=D...
12